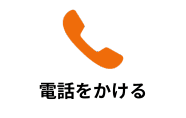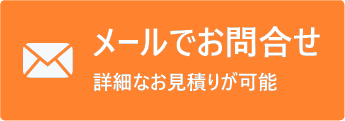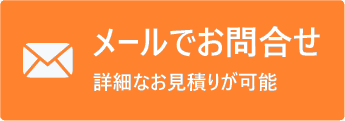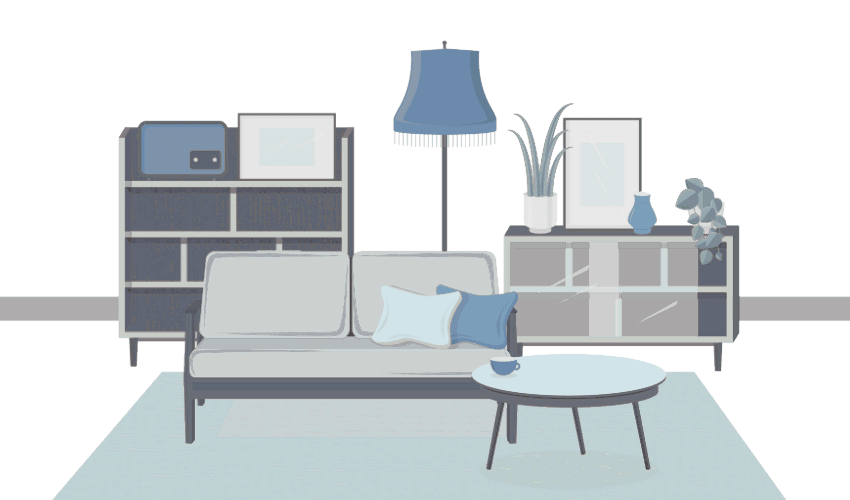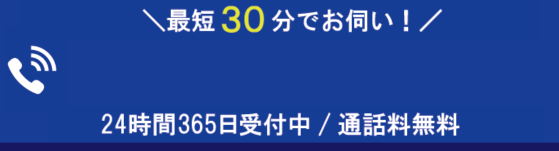釣竿の捨て方8選!プラケースの処分やリールの捨て方も紹介
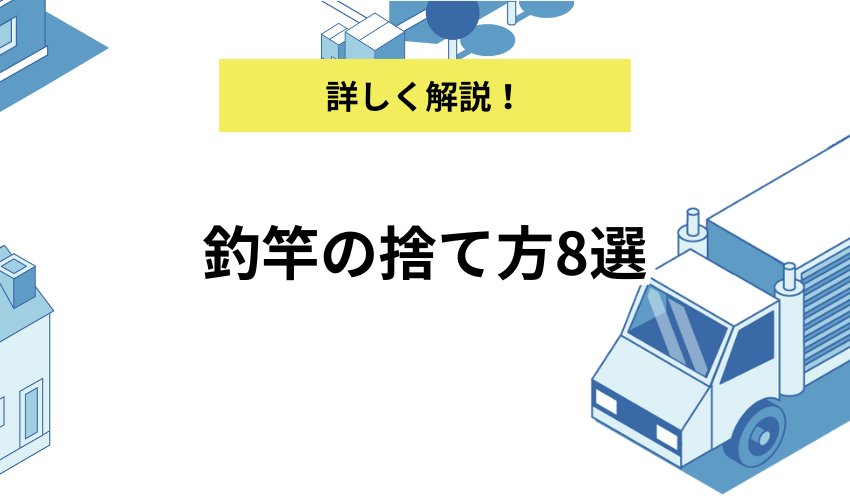
 お客様
お客様 お客様
お客様釣りを趣味とされる多くの方々にとって頭を悩ませるのが、不用となった釣竿の処分。不用品の適切な処分方法を知ることは、環境への配慮と社会のルールを守る上で重要です。
釣竿の処分方法には、自治体の規則に基づくごみ出しやリサイクルショップまたは釣具専門店への持ち込み、フリマアプリでの販売があります。また、不用品回収業者を利用すれば、多数または破損した釣竿も簡単に処分が可能です。
本記事では、釣竿を含む釣具を環境に優しく、かつ効率的に処分する方法について紹介します。
目次
釣竿の捨て方8選
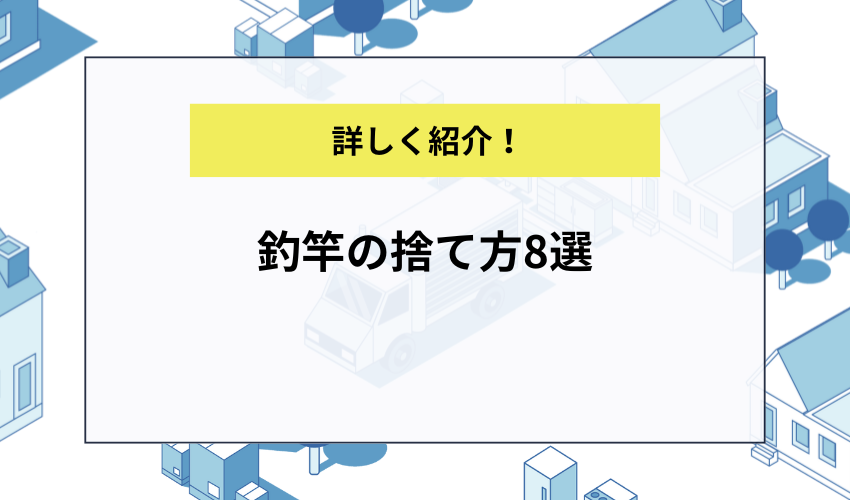
釣竿を処分するには、いくつかの選択肢があります。処分方法は以下の通りです。
- 自治体を利用して釣竿を処分する
- リサイクルショップに持ち込む
- 釣具専門店で買い取ってもらう
- フリマアプリに出品する
- 友人や知人に譲る
- 身近で欲しい人を探し譲る
- 分解して釣竿のパーツを再利用する
- 不用品回収業者に依頼する
各処分方法を適切に理解し、自分のニーズに合った処分方法を選択してください。
自治体を利用して釣竿を処分する

釣竿の処分を考える際、最初に検討すべきは居住地域の自治体の利用です。自治体によっては、釣竿を「普通ゴミ」扱いで受け入れるところもあれば、「粗大ゴミ」として手続きが必要な場合もあります。
以下では、「普通ゴミ」と「粗大ゴミ」、それぞれの処分方法を解説します。自治体で釣竿を処分したい方は、ぜひ参考にしてください。
釣竿を普通ゴミで処分する方法
釣竿は、自治体の定めるサイズに応じて「普通ゴミ」として処分できます。
- 横浜市:全長50センチメートル以下に小さくした釣竿
- 千代田区:30cm以下の釣竿
中身が見える透明または半透明の袋に入れて、決まった場所へ出します。処分基準は地域によって違うため、事前に自治体のホームページを確認または直接問い合わせて確認してください。
また、釣竿の素材によって可燃ゴミか不燃ゴミかの区分もあり、一般的に木製は可燃、カーボンやガラス製は不燃ゴミとして扱われます。
折れたり尖ったりしている釣竿は作業員の安全を考慮し、先端を紙などで覆ってから袋に入れましょう。
釣竿を粗大ゴミとして処分する方法
処分したい釣竿が自治体の規定より大きい場合は、「粗大ゴミ」として処分する必要があります。基本的な粗大ゴミの処分方法は以下の通りです。
自治体の指定する方法で粗大ゴミの申し込みを行います。インターネットや電話での申し込みが可能です。
金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで粗大ゴミ処理券(自治体により名称は異なります)を料金分購入し、釣竿に貼り付けます。その後、指定された収集日に釣竿を収集場所に出しておきましょう。
原則雨天の場合でも粗大ごみの回収は行われます。油性マーカーを使用して、受付番号や氏名をはっきりと書き込んでください。
リサイクルショップに持ち込む

オフハウスなどのリサイクルショップの利用は、不用品を新しい持ち主に繋げる有効な手段です。まずは、対象のリサイクルショップが釣竿を受け入れているか確認します。
受け入れの確認が取れたら、釣竿を清潔にして可能な限り良い状態にして持ち込んでください。取り引きが成立したら、現金または店舗の規定に応じた支払い方法で買取金を受け取ります。
買取金は釣竿の状態や需要に応じて大幅に変わります。複数のショップの条件を比較し、最も有利な取り引きができるリサイクルショップを選びましょう。
釣具専門店で買い取ってもらう

釣り具専門店は、専門知識を持つスタッフが丁寧に査定し、適正価格での買い取りを提案してくれます。釣具専門店「タックルベリー」では、店舗買い取りはもちろん、WEB宅配買取、通信買取が可能です。
店頭の場合は、その場ですぐ査定してくれるため、忙しい方でも安心して利用できます。また、リサイクルショップと同じく、店舗によって査定額は大きく変わります。
 不用品回収スタッフ
不用品回収スタッフフリマアプリに出品する

近年、不用品をメルカリのようなフリマアプリで売却するケースが増えています。状態が良ければ、それなりに利益も上がります。
出品前に釣竿の状態を確認し、汚れている場合はできる限り綺麗にしてください。取り引きは対面で行う訳ではないため、詳細な説明と明るい写真が重要です。
購入者が現れたら釣竿を丁寧に梱包し、約束の期間内に発送します。釣竿が購入者のもとに届いたら、評価をして取り引き完了です。
取り引きは個人間で行われるため、丁寧な対応が必須です。トラブルを招かないためにも、まめにアプリを確認しましょう。
友人や知人に譲る
使わなくなった釣竿は友人や知人に譲る方法もあります。釣り仲間の間で譲り合うのもよいですし、釣りを始めてみたい友人がいれば、釣具を譲ってあげれば友人も釣りを始めやすいのではないでしょうか。
釣り素人から見ると魚の種類によって竿や仕掛けなどの違いはわからないものです。初心者に釣具を譲るときには、釣り方や仕掛けなどわかりやすく伝えると安心して始められるでしょう。釣竿を譲って釣り仲間が増えたら楽しいですよね。
身近で欲しい人を探し譲る
友人知人で釣具が欲しい人がいない場合は、ジモティーや自治体の広報誌などを活用して近所で釣具を探している人を探してもよいでしょう。ジモティーは家で不用になった品を、近所に住んでいる人に譲り合える地域密着型の情報サイトです。
ジモティーや自治体広報に投稿では、釣竿の状態をできるだけ正確に伝えることが大切です。写真や購入時期、汚れや破損など写真を付けて丁寧に説明しておくと、あとでトラブルになることはありません。
分解して釣竿のパーツを再利用する
釣竿はロッド、リールなどさまざまなパーツが使われています。処分する前にまだ利用できるパーツは分解して再利用してはいかがでしょうか。
日頃から釣竿を手入れしていると分解にも慣れて、パーツが劣化したときも交換して使えるようになります。釣具は釣りたい魚によって種類が違いますし、釣具パーツごとで価値が変わってくる品物でもあります。
上手に分解して使い分けると同じ釣竿でも長く使うことができますよ。
不用品回収業者に依頼する

不用品回収業者は、大型の不用品や特殊な処分が必要なアイテムを自宅から回収してくれるサービスです。利用の際は、電話またはインターネットで予約し、見積もりを出してもらいます。
予約した日に立ち会いし、料金を支払えば完了です。信頼できる業者を選ぶためには、許可の有無や無料の見積もり、追加費用が発生しない業者を探しましょう。
不用品を安心して処分したい場合は、「不用品回収センター」への相談がおすすめです。信頼できる専門家のサポートにより、不用品の処分をスムーズで効率的に進められます。
釣竿を不用品回収業者で処分するメリット
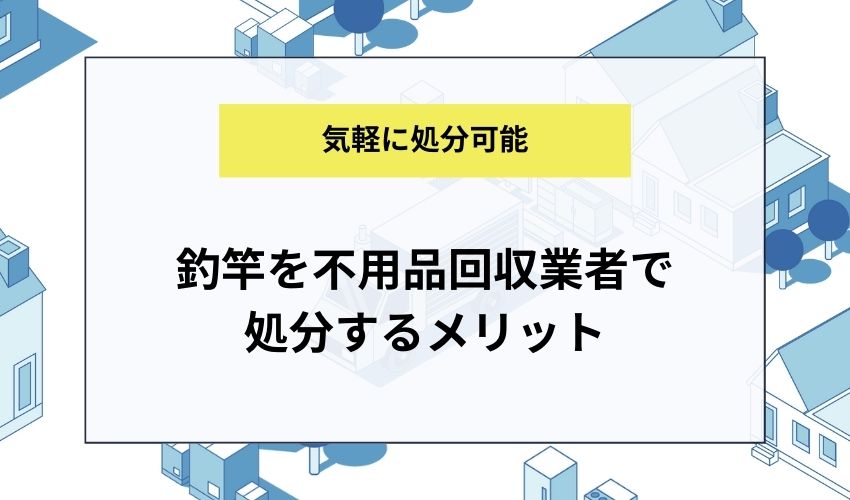
釣り愛好家にとって、不要になった釣竿の処分は意外と頭を悩ます問題です。特に多くの釣竿を所有している場合や使用できなくなった釣竿をどう扱うかは、簡単に解決できるものではありません。
以下では、不用品回収業者を通じて釣竿を処分するメリットを解説します。
大量の釣竿も簡単に処分できる
不用品回収業者を利用する最大のメリットは、大量の釣竿でも簡単に処分できる点です。
長年にわたって釣りを趣味としてきた人々は、健康上の問題や趣味の変化などの理由で、新しい釣竿への交換を考えることがあります。大量の釣竿の処分で頭を悩ませている場合でも、不用品回収業者は不要になった多くの釣竿を一括で回収してくれるため、個別に処分する手間を省けます。
 不用品回収スタッフ
不用品回収スタッフ折れた釣竿も手軽に引き取ってもらえる
時には大物の魚を釣ることもあるため、使用しているとすぐに折れたり壊れたりしやすいです。一度故障すると自分での修理や廃棄が困難なことがしばしばあります。
不用品回収業者を使えば、どのような状態の釣竿でも気軽に引き取ってもらえます。これにより、不要になった釣竿を手間なく、環境に優しく処分が可能です。
 不用品回収スタッフ
不用品回収スタッフ釣竿や釣具を買取してくれるお店
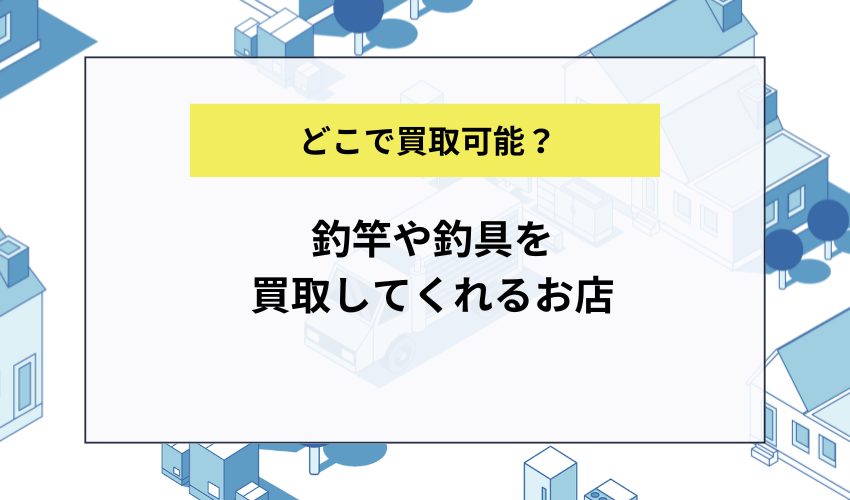
- タックルベリー
- ウェイブ
- RAFT
釣竿や釣り具を買取してくれるお店は店舗買取りのほか出張買取、宅配買取などの形態が全国にあります。前の章で紹介したタックルベリーは全国展開している釣り具チェーンで買取成約率96%と安定した買取をしてもらえるでしょう。
ウェイブは東京・大阪・福岡など主要都市に店舗を構える釣り具の買取専門店です。24時間メール査定可能で最短即日出張してくれます。
釣り具買取店はチェーン展開している店舗のほかに個人店も多いです。たとえば、関東エリアの釣具買取店RAFTは完全予約制で、個人店ならではの専門知識と査定力で丁寧に査定してくれます。
釣竿を高く売却するポイント
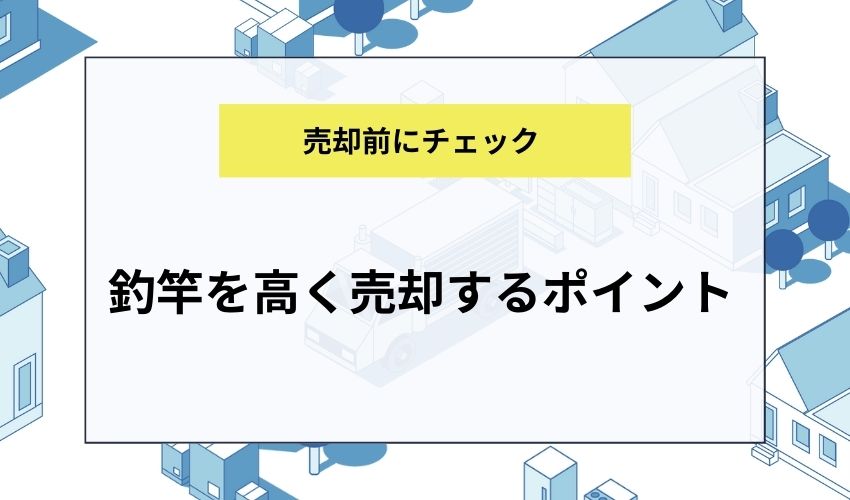
釣竿を高く売却することで、新しい釣り具への投資に回すことが可能です。以下では、釣竿を高く売却するためのポイントについて、具体的な方法を紹介します。
これらのポイントを押さえて賢く釣竿を売却し、日常をさらに充実させましょう。
付属品を揃えて売却する
釣具を売却する際、付属品の有無は査定額に大きく影響します。釣竿だけでなく、リールや収納バッグ、ルアーセットなど釣りに必要な付属品全てを揃えて売ることが重要です。
付属品が揃っていると、購入者は追加の購入なしで直ちに釣りを始めることができるため、商品の魅力が格段に上がります。特に、商品が元の箱や説明書とともに提供される場合、その価値と査定額はさらに増加します。
今後、売却予定がある場合、使用しない付属品は清潔に保管しておくのがおすすめです。
出来るだけ綺麗な状態にする
釣竿は海水によってサビやシミが発生しやすくなります。汚れていると釣竿の価値を著しく下げるため、購入時から売却を見越している場合、使用後の適切な手入れが重要です。
使用後に釣竿を真水で丁寧に洗い流し、柔らかい布で水分を優しく拭き取ることで綺麗に保管できます。
洗剤の使用は避けましょう。利用する場合は、専用の洗剤をご購入ください。
釣竿を処分するときの注意点
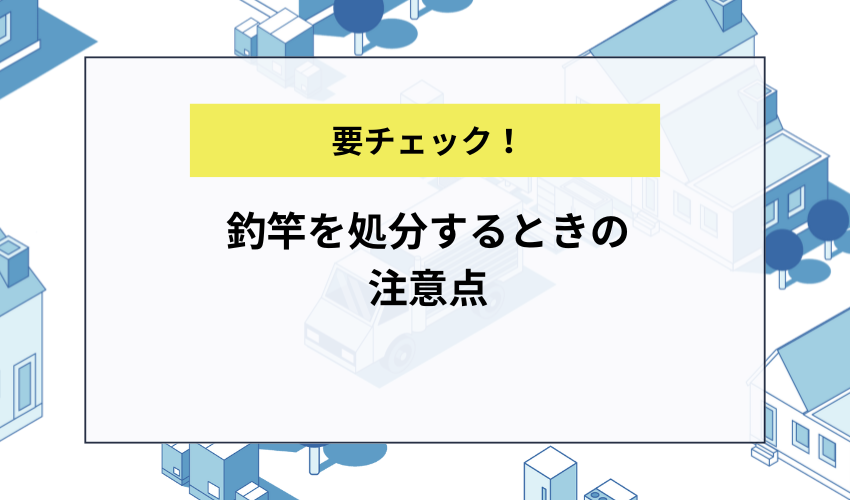
本章では、釣竿を処分する際に気を付けたいことをお伝えしています。後の章でも詳しく紹介していますが、釣具にはさまざまな付属品があり、材質によって処分時の扱いが異なります。
また、解体する場合にも、ロッドの構造上解体が難しい品物もあります。釣竿を捨てる場合も売却する場合も最後まで丁寧に扱うことが大切です。
解体する場合はケガに注意
釣竿は餌釣りで4~5m、ルアーフィッシングで2~3mあります。通常は1~1.5mの長さで仕舞えるようになっていますが、自治体のごみのサイズによっては小さく解体する必要が出てきます。
竹の竿は切れるので解体は比較的楽ですが、カーボン素材の竿になると、接続部がしっかり留められていて解体が難しい場合があります。無理に解体すると、プラスチック部分が飛び散るなどして、ケガする可能性があるのでご注意ください。
解体する場合にはケガに注意して行なってください。
配送時は壊れないように丁寧に梱包する
釣竿は繊細な品物です。売却や人に譲る際に配送するときには壊れないように注意しましょう。
特に売却時にはリールやルアー、ガイドなど価格を左右する高級パーツが含まれますので、破損すると値段がつかなくなるかもしれません。ヤマト急便やゆうパック、佐川急便では160~180cmサイズの配送ができますので、釣竿を気包材や段ボールでしっかり巻いておきましょう。
安定させるためには穂先はきつく梱包し、釣竿が動かないようにしておくと安心です。
使わない場合はすぐに売却する
釣竿には寿命の基準はありませんので、大切に使い続ける人は20~30年同じ釣竿を使っていても問題はありません。ただし、釣竿も負荷をかけた分だけ肉眼で見えないほどの細かいクラックが入ったり、長時間の熱や紫外線でダメージを受けることがあり年数が経つともろくなってきます。
また、釣具のデザインや機能には流行もあります。使わなくなった釣竿は、状態がよいうちに売却を検討した方が高値で売却しやすいでしょう。
リールや釣竿のプラケースの処分方法
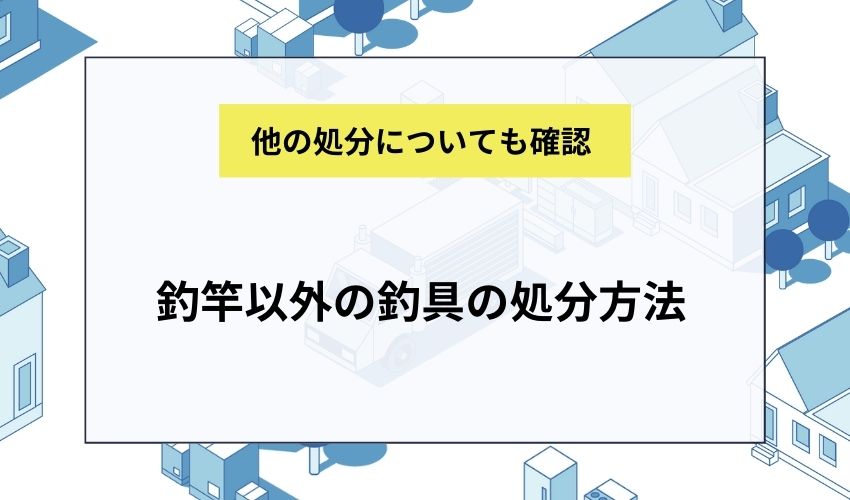
釣りを楽しむ上で必要不可欠なアイテムである釣具ですが、使わなくなったり、古くなったりした際の処分方法に困ることがあります。以下では、釣竿以外の釣具、すなわちリールやルアー、そして釣具購入時に付属するプラケースなどの処分方法を紹介します。
リールの処分方法
リールの素材に応じて、処分方法が異なるため注意が必要です。例えば、横浜市では以下のように分別します。
- 金属製:金属類のゴミ
- プラスチック製:可燃ゴミ
- 充電式のリール:粗大ゴミ
自治体によって分別が異なるため、事前に確認することが大切です。
電動リールはバッテリーを外してから処分してください。
ルアーの処分方法
ルアーは材質によって処理方法が異なります。例えば、横浜市では以下のように分別します。
- 金属製のルアー:金属類のゴミや不燃ゴミ
- それ以外:基本的に可燃ゴミ
また、ルアーはリサイクルショップやフリマアプリを通じて再販することが可能です。特に人気のあるブランドのルアーは、個々の買取価格が低くても、まとめて売れば意外と高い金額になることがあります。
ルアーに針がついている場合は、フックを新聞紙で丁寧に包み、包装紙の上にマジックで品名と「危険」と書いて不燃ゴミとして出してください。
釣竿やルアーを買った時についてくるプラケースの処分方法
釣り具付属のプラケース処分には、まず自治体のリサイクルルールを確認しましょう。多くのプラケースはプラスチック製ですが、リサイクルできるかは地域によって異なります。
主にPETボトルや一部特定プラスチックがリサイクル対象です。プラケースがリサイクル不可の場合、通常は可燃ゴミとして処理されます。
プラケースが割れている場合は作業員の安全を考慮して、ビニール袋に入れて口を縛ってから処分しましょう。
釣竿の処分は「不用品回収センター」へ
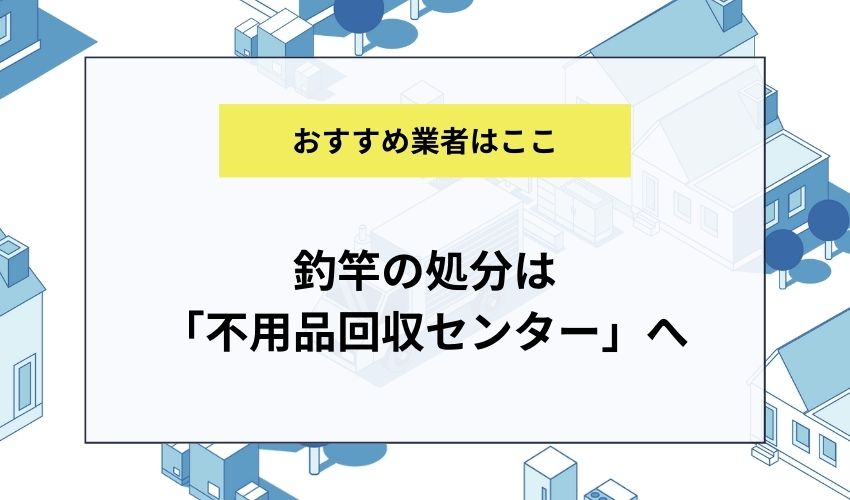
不用品回収センターは、釣竿をはじめとする不用品の処分を手軽に、そして環境に優しく行なってくれる最適な選択肢です。不用品回収センターを利用することで、煩わしい処分作業から解放され、手軽に不用品を処分できます。
以下は、「不用品回収センター」の詳細についてです。
不用品回収センターの詳細

| 特徴 | ・年間50,000件以上の回収実績 ・追加費用は一切なし |
|---|---|
| 料金 | ・SSパック:定価10,000円からのサービスがWEB限定で4,800円に |
| 回収可能な不用品 | ・釣竿を含むほとんどの家庭用品や事務用品などの幅広いアイテム ・回収不可能な物には、著作権や名誉権を侵害する物、爆発物、盗品など |
| 買取制度 | あり |
| 電話番号 | 0120-949-966 |
| 公式HP | https://suisan-portal.jp/ |
不用品回収サービスでは、最短即日の回収が可能です。特別な手続きは必要ありません。
24時間対応で、深夜や早朝の依頼も受け付けており、単品回収からゴミ屋敷の清掃まで幅広く対応しています。さらには高価買取のオプションがあり、WEB限定割引やGoogle MAP口コミ割引などの特別プロモーションを併用することで、さらにお得にサービスをご利用いただけます。
処分後に新しい釣竿を購入するときのチェックポイント
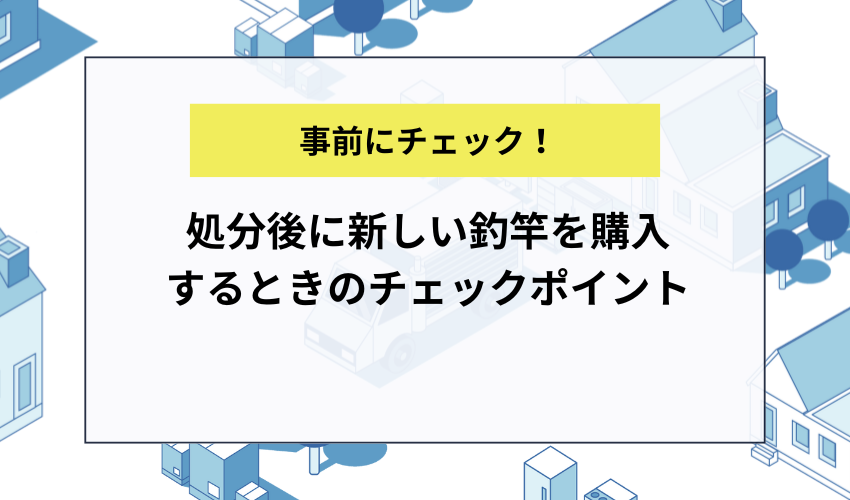
釣竿を処分したからといって釣りをやめる人は少ないでしょう。釣竿を処分してから新しい釣竿を購入するときには、確認しておきたいことがあります。
釣りを始めて間もない方でも、釣りのスタイルによって欲しい竿は変わってくると思います。本章では釣竿処分後に新しい釣竿を購入するポイントをお伝えします。
自分の釣りスタイルを確認する
新しい釣竿購入前には、自分の釣りスタイルを確認しましょう。どこで釣るか何を釣るかで竿も仕掛けも変わりますよね。
釣りは本当にジャンルが広いので、自分にしっくりくるスタイルは経験を重ねないとわからないこともあります。自分の好きな釣りを追及するのもよいですし、新しいスタイルにチャレンジするのも楽しいですよね。
ネットショップや釣具屋に行くとどの釣具も魅力的にみえてくるので、あらかじめ釣りスタイルをどうするか確認して、購入時迷わないようにしましょう。
扱いやすさで選ぶ
前項のスタイルにも通じることですが、釣りを楽しむうえで扱いやすさは大切なポイントです。高級の竿を持っていても、目的の釣りと相性が悪ければ宝の持ち腐れです。
釣竿のスペックも基準がさまざまです。たとえば、ルアーロッドであればウエイト・サイズ・ラインの基準の確認は大切ですし、投げ竿では重り負荷を考えた方がよいでしょう。
購入時には、素材・重さ・長さなど仕掛けにあった適切な釣竿を選ぶようにしましょう。
釣竿の素材で選ぶ
上釣りスタイルが決まっている人は、釣竿の素材についても購入時にはよく確認しておきましょう。一般的に釣竿の素材はカーボン・グラスファイバー・ボロン・竹があります。
カーボンは軽量で感度もよく弾性率に富んでいます。グラスファイバーは重さはありますが、粘り強く折れにくいというメリットがあります。
軽量ほど高価ではありますが、カーボンとグラスファイバーのメリットを活かした複合品も多くでています。ボロンや竹は、目的がはっきりした高級品が多いです。
【まとめ】釣竿を賢く捨てよう
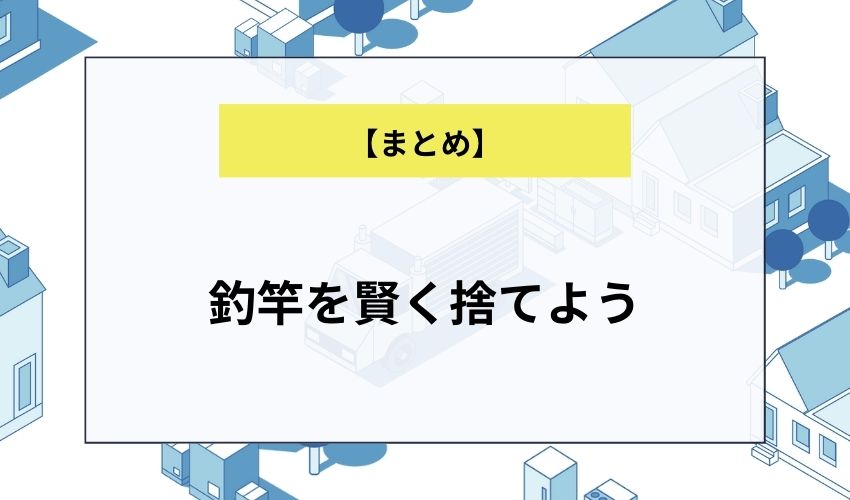
この記事では、釣竿の処分方法を紹介しました。自治体の利用やリサイクルショップの利用、フリマアプリの利用など多様な処分方法がありますが、不用品回収業者がおすすめです。
不用品回収業者に依頼する場合は、信頼できる業者選びが重要です。許可証の有無や見積もりの無料提供、透明な料金体系を持つ業者を選びましょう。
大切なのは、釣竿の状態を正確に把握し、最適な処分方法を選ぶことです。また、釣竿以外の釣具の処分についても、同じように適切な方法を選びましょう。