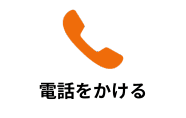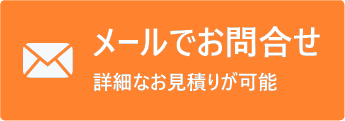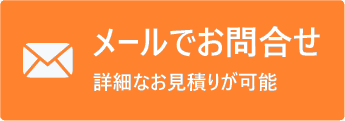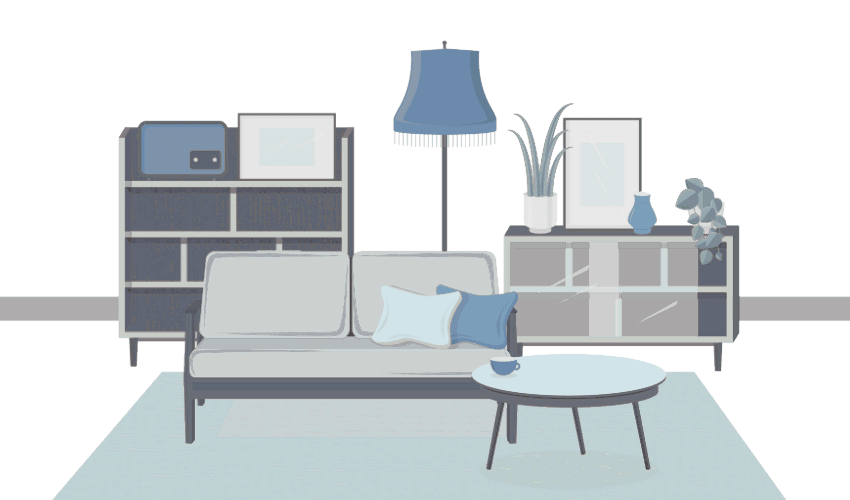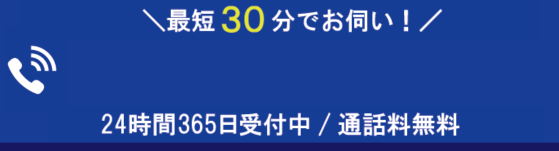生木を処分する方法は?処分する際の注意点と費用を抑えるコツを紹介!
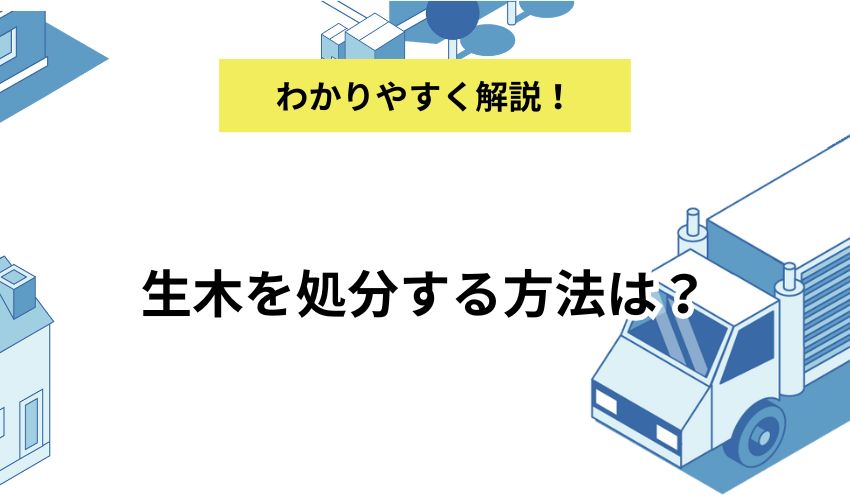
 お客様
お客様 お客様
お客様生木の処分方法に、悩む人は多いのではないでしょうか。生木は少量でごみ袋に収まる程度であれば、自治体での処分が可能です。
生木は可燃ごみ扱いになることが多いですが、野焼き行為は法律で禁じられています。本記事では生木の処分方法や生木を処分する際の注意点・処分費用を抑えるポイントなど、生木を処分する際に知っておきたい情報を詳しく紹介します。
- 生木を処分する方法5選
- 生木を処分する際の注意点
- 生木の処分費用を抑えるポイント
目次
そもそも生木は一般廃棄物?産業廃棄物?
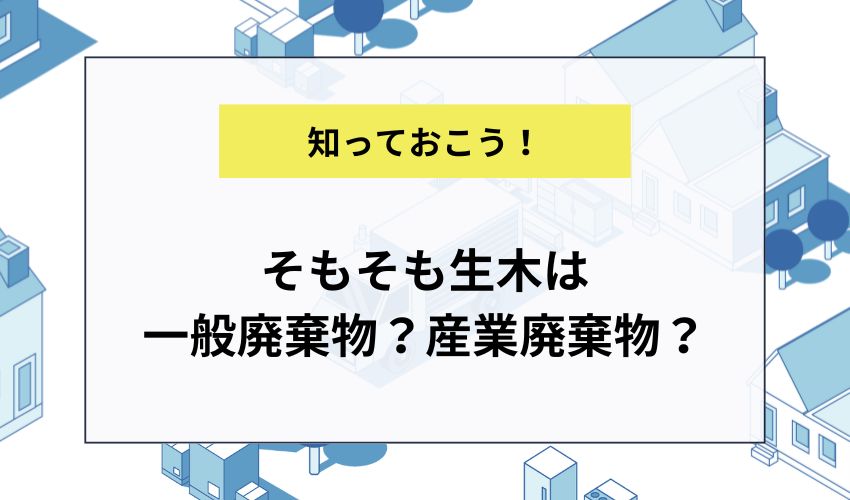
生木という言葉は日常生活であまり見かけない表現で、伐採したばかりでまだ乾燥していない状態の木や剪定した枝を指します。そもそも生木を処分する際、一般廃棄物になるのか、産業廃棄物になるのかは迷うところです。
一般的に建設工事の際に排出された生木は産業廃棄物となり、建設工事に関係なく排出された生木は一般廃棄物となります。つまり、業者が関わり処分を行う生木は産業廃棄物で、自分で剪定した枝や生木は一般廃棄物として扱われ自治体でも処分が可能です。
生木を処分する方法
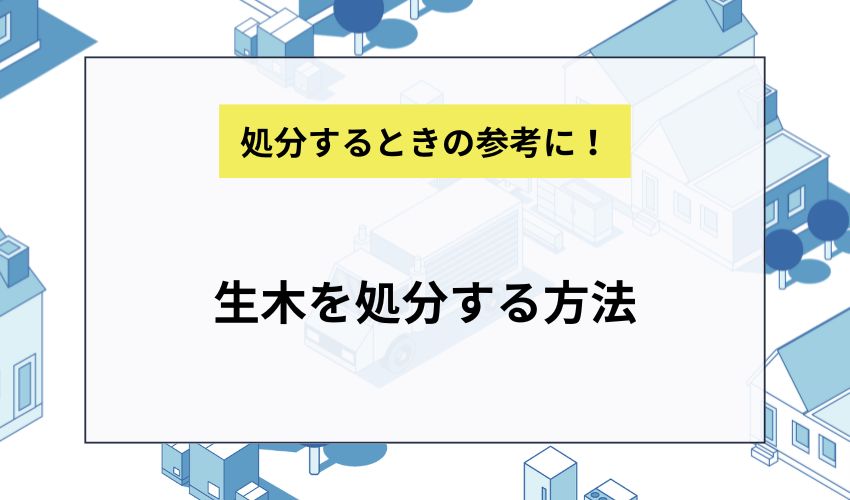
自宅の庭木を手入れした際に出る剪定枝や木材の処分に、困った経験のある方も多いでしょう。どのように出せば良いのかさえもわからない生木を処分するには、いくつかの方法があります。
本章では、生木を処分する方法として5つを紹介します。自治体処分では、自治体例も混じえながら解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
- 自治体で処分する
- 造園・伐採業者に相談する
- 木くずなどのリサイクル業者を利用する
- 産業廃棄物として処分する
- 不用品回収業者に依頼する
自治体で処分する
自治体を利用する場合は、一般ごみとして処分するかごみ処理施設へ持込み処分するかの2通りの方法があります。生木は可燃ごみ扱いとなるのがほとんどですが、自治体により粗大ごみとなる場合もあるので、事前に自治体ルールの確認が必要です。
本章では、生木の処分として一般ごみ処分と持込み処分を、一つひとつ詳しく解説します。
自治体で一般ごみとして処分する
一般家庭で伐採や剪定した木や枝は、可燃ごみとして処分ができます。例を挙げると、北九州市の自治体で、剪定枝を処分する方法は次の通りです。
太さ10cm以内の枝を長さ1m・重さ10kg以内の束とし、指定袋に入れて一般ごみの収集日に指定場所へ搬出するようになっています。中間市では粗大ごみ扱いとなり、搬出の条件は1本ずつの生木直径10cm以上、5本までなら直径10cm未満・長さ2.5m未満でした。
各自治体により大きさや重さは細かく決められており、ごみの種類も異なる可能性があるため、居住地域の自治体ルールを確認し処分を行う必要があります。
各自治体のごみ処理施設に搬入する
可燃ごみでは出せないほど大きな生木の場合、各自治体のごみ処理施設に搬入する方法があります。たとえば北九州市では新門司工場と皇后崎工場に持込み可能で、手数料は10kg100円です。
中間市でのごみ処理施設は、遠賀・中間リレーセンターです。草・剪定枝・木材の持込みは1日に200kgまで、料金は10kg未満220円・10kg以上10kgごとに220円が必要となります。
ごみ処理施設の条件に沿って搬出を行わなければならず、事前申し込みが必要な施設といつでも持込み可能な施設があるので確認が必要です。
造園・伐採業者に相談する
庭木の伐採から処分まで一気にまかせたい場合は、生木を扱うプロである造園や伐採業者に相談する方法があります。自分で何もする必要がなく、自力では時間のかかるところを専門の技術と機材により短時間で処分が可能です。
たとえば自分で庭木の手入れをした場合、生木の処分だけを引き受けてくれる業者もあります。ただし事業者への処分依頼となるため生木は産業廃棄物扱いとなり、費用が割高になる可能性もあるので注意が必要です。
また木材の買取を行っている園芸・伐採業者もあるため、査定を依頼するのも一つの方法です。
産業廃棄物として処分する
個人宅から出た生木であっても造園事業者などの事業所に依頼した場合、産業廃棄物としての処分となります。産業廃棄物の処理業者に依頼すれば生木処分の知識と豊富な経験があるため、条例に沿った適切な処分を行ってくれるので安心です。
ただし、産業廃棄物の処分では、処分費用が高くなる可能性があるので注意しましょう。
不用品回収業者に依頼する
回収の幅の広さで挙げられるのは、不用品回収業者に依頼する方法です。一般家庭からでも事業所からでも関係なく、不用品回収業者であれば生木の回収が可能で便利に利用できます。
一般廃棄物・産業廃棄物関係なくというのは、不用品回収業者が両者の許可証を取得している場合に限ることを付け加えておきます。一般家庭から生木を搬出して欲しい場合は、「一般廃棄物処理業許可証」の有無を確認しておいてください。
不用品回収業者は解体から搬出まですべての作業をまかせられるので、処分費用はかかるものの自力で何もかも行うことを思えば楽です。生木だけではなく、ほかにも処分したいものがあればまとめて処分ができるため、一気に片付けられます。
生木を処分する際に気を付けたいこと
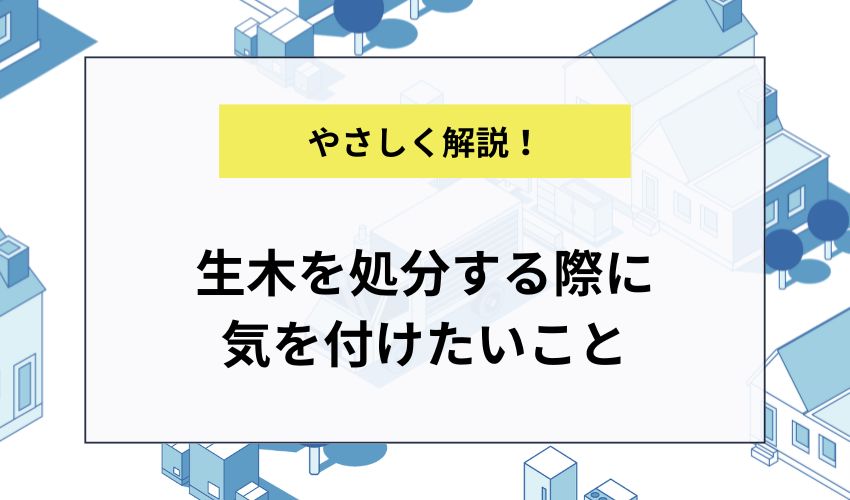
生木を処分する際に、気を付けておきたいことがあります。本章では注意点として、6つを一つひとつ詳しく解説しているので、注意深く読み進めて生木を正しく処分するよう気を付けてください。
- 自分で生木を燃やさない
- 生木を濡らさないようにする
- 害虫の発生を防ぐため早急に処分する
- 生木を放置しておくと火災のリスクが高くなる
- とげなどがないかを確認しておく
- 土は他の処分方法を検討する
自分で生木を燃やさない
自宅の庭木で出た生木は可燃ごみとなるため、自分で燃やしても良いと思う人もいるのではないでしょうか。野外での焼却は法律で禁止されており、違反した場合は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくは両方の罪に問われます。
野焼きは、風の影響で火事の原因となったり不自然な煙によって近所トラブルに発展したりするケースもあります。生木を処分する際は、燃やさないようにしましょう。
生木を濡らさないようにする
庭木の手入れを行う際は晴れた日に行うのが通常で、生木を濡らさないよう気を付ける必要があります。木材を濡らしてはいけない理由は、濡れてしまった木材は重くなり持ち運びが困難となったり、ごみ焼却場の温度を下げたりする可能性があるからです。
木材をすぐに処分できない場合は、ごみ袋大に入るほどの大きさに切って袋に入れ保管するか、比較的大きめの生木であればビニールシートで覆うようにすると良いでしょう。
害虫の発生を防ぐため早急に処分する
湿った生木はとくに害虫が発生する確率が高くなり、病気やアレルギーの原因ともなります。伐採した生木はすぐに、風通しの良い場所へ運び、早めの処分をおすすめします。
冬の時期では害虫の動きも鈍く活動も少ないため、発生の少ない冬の時期に処分するのが最良です。夏の時期となり害虫の活動も活発となるタイミングとなった場合は、早急に処分を行ってください。
すでに害虫が発生している状態なら、自力で処理せず専門の業者に依頼することをおすすめします。
生木を放置しておくと火災のリスクが高くなる
生木は自宅外で放置すると不法投棄となり、罰則の対象となるので注意が必要です。敷地内であっても、生木を放置しておくことで火災のリスクが高くなります。
生木は乾燥させることで軽くなり搬出しやすくなる反面、乾燥した生木は燃えやすくなるのも確かです。置いてある場所が道路に近い場合は、たばこのポイ捨てなどで燃え出す危険性があります。
一度燃え始めると一気に火の手が上がり大火災へと転じかねないので、なるべく生木は放置せずすぐに処分するよう心がけてください。
とげなどがないかを確認しておく
生木のとげ?と思う人もいるでしょうが、生木のとげは鋭く危険なので注意しましょう。とげのある樹木を処分する場合は軍手などで防備し、とげでケガをしないよう細心の注意が必要となります。
指定袋の外からではとげがあるかどうかの判断がつきにくいため、収集スタッフが知らずに袋を持ち上げた際とげが刺さる危険性があります。とげがある場合は、念のため「とげがある」という注意書きを貼っておきましょう。
土は他の処分方法を検討する
生木と一緒に土も処分できると思いがちですが、土は生木と一緒に処分ができません。可燃ごみや持込み施設に排出する場合はとくに、根についた土は取り除いてから処分を行ってください。
自治体では土を処分できないケースが多くあるため、他の処分方法を検討しましょう。時間も手間もかからない方法は不用品回収業者で、土だけではなく大量の不用品をまとめてお得に処分できるパックプランが提供されています。
ホームセンターなどで古い土を引取るサービスを行っているところもあるので、問い合わせてみてください。
生木を処分する場合の費用相場
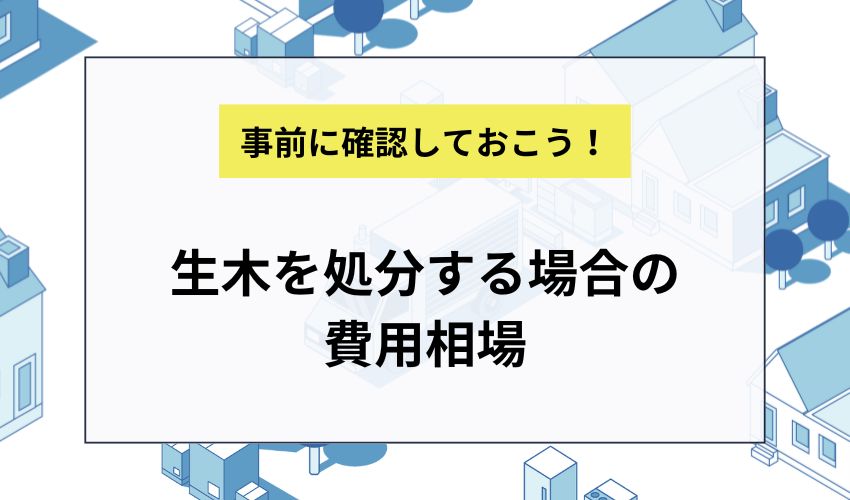
生木を処分する場合は自治体利用が一番安く、費用をなるべくかけたくない人には最適な方法です。業者に依頼するとなると数千円からで、各処分方法別の費用相場は下記表の通りとなります。
各地域での造園業や産廃業者・不用品回収業者をピックアップしての費用相場なので、あくまでも目安として参考にしてみてください。生木だけではなくほかの不用品と一緒に出す場合、不用品回収業者の利用はお得になります。
| 自治体を利用する場合 | 無料~1,000円台 |
|---|---|
| 造園・伐採業者を利用する場合 | 4,000円~1万円台 |
| 産業廃棄物として処分する場合 | 10,000円~ |
| 不用品回収業者に依頼する場合 | 5,000円~ |
生木の処分費用を抑えるポイント
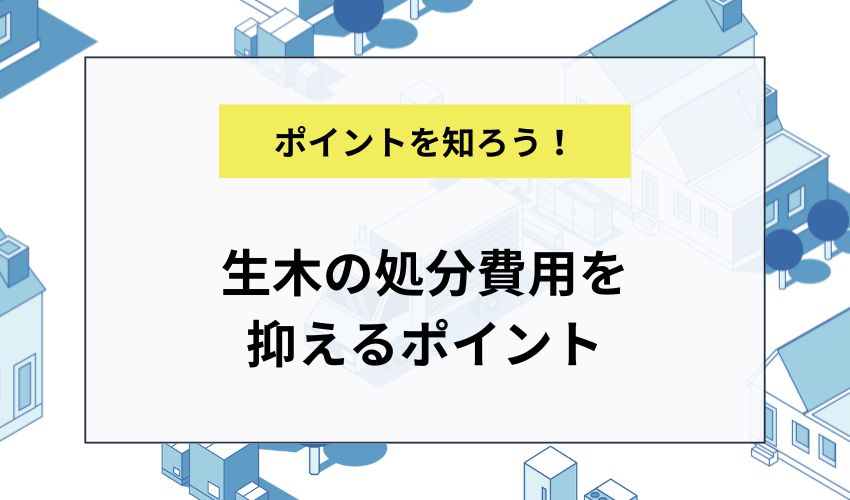
生木の処分を検討する際、できる限り処分費用を抑えたいと思うのは当然です。ひとつの方法として業者に依頼する場合、事前に自分でできることをしておくことが挙げられます。
本章では、生木の処分費用を抑えるポイントとして3点紹介するので参考にしてみてください。
- 自分でできることを事前にやっておく
- 業者に依頼する場合は閑散期がおすすめ
- 生木の処分はまとめて依頼しよう
自分でできることを事前にやっておく
生木に限らず処分費用は大きさや量に比例するもので、事前に自分でできる限り小さく切断しておくと費用を抑えられます。時間や手間がかかりますが、細かくできれば自治体の可燃ごみを利用することも可能です。
業者に依頼する場合でも自分でできることをしておけば、スタッフの作業や作業時間を減らせるため費用削減につながります。自宅で生木の解体を行う場合は、安全な場所を確保しましょう。
解体には、のこぎりやチェーンソーなどの工具が必要となります。必要な道具を用意し、ないものはホームセンターなどでの準備が必要です。
ケガや事故に十分気を付けながら、安全に作業を行ってください。
業者に依頼する場合は閑散期がおすすめ
造園や伐採業者に依頼する場合は、閑散期がおすすめです。5月から10月頃にかけてが繁忙期となるため、閑散期となる11月から4月頃までに依頼すると割引を受けられる可能性があります。
冬場は日程の調整もつきやすく、繁忙期と比べると1割から2割程度の割引が適用される場合があるのです。急ぐ必要がなければ、閑散期を待って業者に依頼することをおすすめします。
生木の処分はまとめて依頼しよう
生木の処分として、複数本まとめて依頼すると割引を受けられる可能性があります。造園や伐採業者に依頼した場合は、自分で切った生木もまとめて処分してくれます。
伐採と処分を別々に依頼するよりも、プロの造園や伐採業者に一括で依頼した方が、費用を安く抑えられる可能性があるでしょう。不用品回収業者の場合は、庭木処分と同時に土や不要な植木鉢もまとめて回収してくれるので便利です。
生木の処分なら不用品回収センターへ!
 生木の処分を検討されているならば、不用品回収センターへぜひご依頼ください。不用品回収センターで回収できないのは、爆発物・火薬・武器などの危険物や液体物・医療関係なので、回収品目の幅広さに自信があります。
生木の処分を検討されているならば、不用品回収センターへぜひご依頼ください。不用品回収センターで回収できないのは、爆発物・火薬・武器などの危険物や液体物・医療関係なので、回収品目の幅広さに自信があります。
生木をはじめとしてほかにも不用品があり、まとめて処分したい場合は、安心の載せ放題定額パックプランをご用意しております。継続してWeb限定割引キャンペーンを実施しておりますので、定額パックをご利用いただきWebから申込みいただくと最大14,200円のお得です。
万が一の事故にも最大3,000万円の請負賠償責任保険に加入しているため、安心してご依頼いただけます。
| 特徴 | 見積もり・基本料金無料 |
|---|---|
| 料金 | SSパック 4,800円~ |
| 営業時間 | 24時間年中無休 |
| 買取制度 | 有り |
| 電話番号 | 0120-949-966 |
| 公式HP | https://suisan-portal.jp/ |
【まとめ】生木の処分は適切に行おう
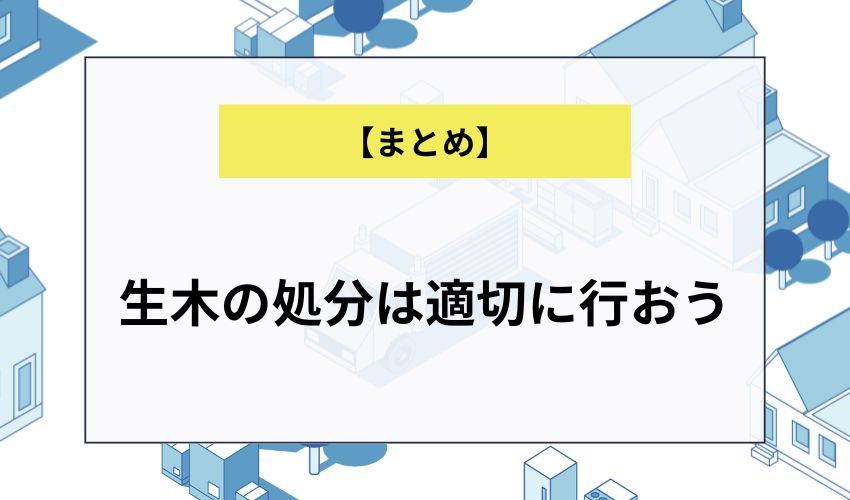
本記事では、生木の処分方法や注意点・費用相場・費用を抑えるポイントを紹介しました。費用を抑えるため自分で生木の処分を行おうとする場合は、ケガや事故に気を付けながら慎重に行ってください。
費用はかかるものの生木の処分を不用品回収業者に依頼すれば、回収後の片付けまでしてくれます。すべての不用品回収業者ではないので、事前の確認が必要となります。
生木の処分には法的な注意点もあるため、適切に行うことが大切です。本記事が、生木の処分を検討している方のお役に立てば幸いです。